北越急行株式会社
代表取締役社長
小池 裕明
1.ほくほく線黎明期
昭和当初、「当時の道路事情、除雪能力、自動車の性能では、冬期の降雪時には全く役にないことから、他の交通機関が必要」と真剣に考えていたのは、松代村(当時)に住んでいた柳 常次氏(当時56歳)でした。柳氏は、山間地から近隣の十日町などへの足として松代自動車株式会社を設立しており、貨物輸送、一般乗り合いバスの運行も行っていた方です。ほくほく線沿線は冬期になれば、多くの雪に閉ざされ、直江津方面、南魚沼方面への移動は難渋なことだったと思われます。
昭和7年、柳氏は代議士へ鉄道敷設の請願書を提出しました。これが、ほくほく線が現在に至る公的誘致運動の始まりと言えます。柳氏の熱い想いは国を動かし、翌昭和8年には、北陸線と上越線を結ぶ(直江津~中頸城~東頚城~中魚沼を貫通して南魚沼で接続)鉄道敷設が貴族院・衆議院で採択されました。
折しも昭和6年9月には清水トンネルの完成により上越線が全通しており、これに接続することにより東京と直結できることから鉄道誘致にかける情熱も一段と高まったことを想像するに難しくないように思います。その後も請願、陳情が繰り返され、当時の採択線は、上越西線(以降北線)と仮称していたようです。
昭和15年には、直江津~安塚~松之山~鹿渡~田沢~倉俣~越後湯沢ルートの南線計画が主張されはじめ、従来から十日町・六日町ルートの北線誘致を行なってきた同盟会は猛然と反論し、以降30年あまり続く北線・南線の誘致合戦=南北戦争が勃発しました。どちらも鉄道を活用した沿線住民の生活確保と商業・観光(当時は湯治観光や織物物産等)を誘客するための経済戦争だったのかもしれません。

雪中を疾走するHK-100
2.ほくほく線の建設開始
昭和39年6月には、現在のほくほく線ルートである北線が工事線に指定され、地元の熱意に触発された地元国会議員の取り組もあり、工事線指定から比較的早く昭和43年4月に六日町駅構内において着工鍬入れ式を迎えました。昭和7年の初陳情から35年の歳月を経ての着工です。その後六日町体育館で開催された起工祝賀会では、 多くの地元関係者が参加し、 未来の大きな夢を語り合ったでしょう。 昭和48年には最後の十日町〜犀潟間の起工式を行われ、六日町〜犀潟間全線の工事が開始されました。

冬期間雪に閉ざされる地域
3.ほくほく線の工事凍結
昭和50年代から60年代にかけては、第二次オイルショックや円高不況が続き国家財政も厳しい時代となっていました。日本国有鉄道の赤字は深刻さを増し破綻状況となっていました。昭和55年には、日本国有鉄道経営再建促進特別処置法(国鉄再建法)が制定、施行され、輸送密度4,000人以下の地方新線は工事凍結されることとなり、予算凍結処置により工事が凍結されてしまいました。
この時点でのほくほく線の工事は、建設費総額794億円のうち415億円が消化され、用地買収82%、路盤工事約58%とかなりの進捗率でありましたが建設を断念せざることになりました。この時の奈落の底に突き落とされた気持ちが、第三セクター方式による工事再開につながったと思いたいのですが、一方で「地方自治体負担とか第三セクターというが、国がやれないものは地方もやれない」といった苦悩の声も多くあったようです。
4.ほくほく線の工事再開
ちょうどその頃、地方新線でほくほく線と同様な条件下にあった久慈・宮古・盛線(岩手県)が全国のトップを切って第三セクター方式による「三陸鉄道」を設立し工事が再開されようとしていました。その後も、栃木県・福島県が同様な新線「野岩線」引き受けのための野岩鉄道が設立されました。新潟県内では当時、廃止地方交通線となった「赤谷線」や「魚沼線」の具体的廃止手順の議論を行うなど、これからお金を出して新しい鉄道を運営することには消極的となっていたと思われます。
窮地打開のきっかけは、昭和58年6月に東京にて開催された北越北線建設促進期成同盟会総会において、田中角栄元首相が「このままではいくら時間があっても埒が明かない。第三セクター方式で行こうではないか」と提案したのがきっかけと語り継がれています。その後とんとん拍子に沿線・県に第三セクター設立準備室が立ち上がり、昭和59年8月には沿線17市町村、地元銀行、企業などの出資による北越急行株式会社が設立、昭和60年には地方鉄道業の免許が交付され、工事着手届けを提出、ほくほく線は、第三セクター線の公団工事として工事が再開されました。

難工事となったトンネル工事
5.ほくほく線の開業28年 (特急「はくたか」運行18年+新生北急10年)
平成元年には、首都圏と日本海側の主要都市を結ぶ基幹鉄道と位置付けられ、ほくほく線経由で北陸本線の富山・金沢と上越線の越後湯沢間にスーパー特急(160㎞/h運転)を運行し大幅な時間短縮を図る高規格化への工事変更が行なわれました、平成9年3月、工事着工より29年、初陳情からは64年の歳月を経て、冬期間は、陸の孤島と化す山間の豪雪地帯を何とかしたいという先人たちの悲願がそれぞれの時代に翻弄されながらも代々受け継がれることによって、新幹線に近い容で開業し、今年で28年目を迎えます。この間、約7,200万人のお客さまにご利用いただきました。

ほくほく線六日町駅開業式

開業を喜ぶ沿線住民
本年は、北陸新幹線の金沢延伸開業より10年を迎えます。北陸新幹線金沢開業により在来線特急「はくたか」が廃止され、本来の地域鉄道として日々ご利用いただくお客さまの生活路線、地域間の交流、移動を担う交通インフラとしての使命と責任を担っていると共に、沿線の皆さまとの協働により、乗って楽しい、降りて楽しいイベント等も開催してきました。

特急 はくたか
今年度は、スノータートル、光と音の饗宴芸術祭列車「JIKU#13HOKUHOKU-LINE」などの人気イベント列車の運行並びにパンや地元クラフトビール等の販売を行うコンコースマルシェ、鉄道むすめ・松代うさぎのプロモーション、鉄道により親しみを持っていただく基地まつりなどを予定しています。

芸術祭列車「JIKU#13HOKUHOKU-LINE」
北陸新幹線金沢開業10周年に合わせ、「えちごトキめき鉄道」「しなの鉄道北しなの線」「あいの風とやま鉄道」「IRいしかわ鉄道」各社においても多彩なイベントが開催されることと思います。弊社においてもこのイベントと連携させていただき、「特急はくたか」への感謝、懐かしく回想していただける取組み「Remember Ltd.Exp HAKUTAKA」を展開したいと考えています。
これからのほくほく線、地域の公共の足を考える時、先人の熱き精神を受け継ぎ、しっかりと歴史を学び、選択を誤ることのないよう行動していかなければいけないと考えています。

十日町駅コンコースマルシェ

鉄道むすめデビュー列車
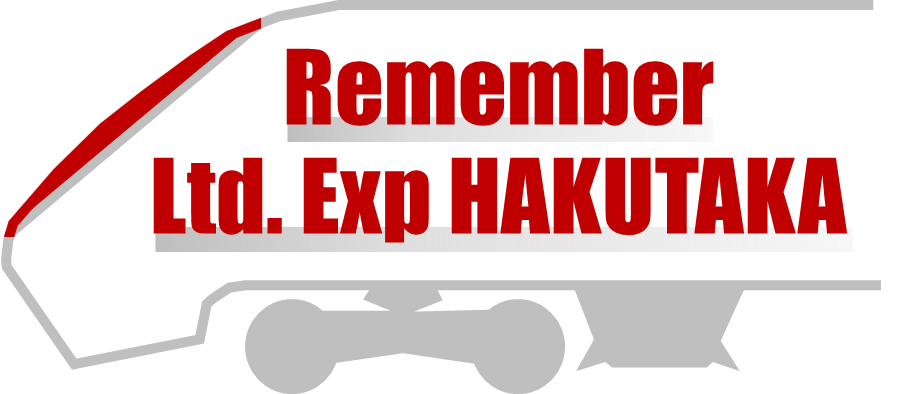
リメンバー特急はくたかロゴ